朝、光がまぶしいというより鋭い。
情報の刃(データエッジ)が瞳の裏を切る。
それでもSNSを開く。今日もまた誰かの感情が溢れてる。
全部が感情飽和圏(Emo-Saturation Zone)にある。
ニュースも、広告も、友達の投稿も。
どれも同じ温度で鳴り響くから、
心の防音壁が機能不全を起こす。
この街ではそれを共感過多症(Empathic Overrun)と呼ぶ。
気づけば人の痛みに過剰反応する自分がいる。
痛みのミラーリング(Pain Reflection)で心拍が乱れる。
本当は誰も傷つけてないのに身体が反応してしまう。
それを説明できないから「病気」って言ってるだけ。
感情を抑えたら楽になるのかもしれない。
抑制は思考麻酔(Cognitive Sedation)になる。
痛みのない世界は、安全で、退屈で、虚ろ。
そんな場所で生きるくらいならわたしは過敏なままでいい。
誰かの笑い声で泣いて、
誰かの涙で笑って、
感情の波形を翻訳しながら生きてる。
この時代のわたしたちは、
たぶん心のセンサーを剥き出しにして歩いてる。
それを隠さない勇気を病気と呼ぶなら、
わたしはずっと治らなくていい。
感受性の病気 #共感過多症 #現代の生きづらさ #感情資本主義 #モカティック美学 #SoftRealism #思想と感情
心理学的に言えば感受性とは過剰な脆さではなく情報と感情の受信装置。
世界のノイズを痛みとして正確に受け取る能力。
だからこの生きづらさは異常じゃなく世界のリアルタイム翻訳。
心理学的解説:感受性という認知の過負荷
心理学的に言えばいわゆる感受性が強い人は、
高感度処理特性(Highly Sensitive Processing)を持つ。
つまり脳が他人の感情・音・光・温度・言葉のトーンまで、
平均より細かく拾ってしまう。
研究ではこの特性を持つ人の脳の島皮質(insula)や前帯状皮質(ACC)が、
他人の感情刺激に反応する際により強く活動していることが分かっている。
共感をつかさどるミラーニューロンのネットワークも過剰に働く。
だから——
他人の痛みを理解する前に感じてしまう。
これは共感的共鳴(affective resonance)と呼ばれる。
その瞬間、脳は自分と他人を区別できなくなる。
日常で「疲れる」と感じるのは、
感情を受信する力が強すぎて自己境界(self-boundary)が薄くなるため。
その結果、他人の感情の洪水に呑まれて、
自分の感情がぼやけていく。
生きづらさの正体は感度と世界の速度のズレ
現代社会は情報処理速度が感情処理速度を上回っている。
心が理解する前に世界が次の話題へ移る。
この認知ラグ(cognitive lag)が慢性的な疲労と不安を生む。
感受性が高い人ほど感情をひとつずつ丁寧に消化しようとする。
でもその間にも新しい刺激が流れ込む。
脳の中では情報の渋滞が起こり、
それが「生きづらさ」として体験される。
それでも「感じる力」は壊さない方がいい
心理学的には、感受性はリスクであり、同時に創造性の母体でもある。
多くの芸術家・研究者・思想家が高感度処理特性を持っていたことが知られている。
脳が痛みを細かく拾うほど他者や世界への想像力が育つ。
だから「感受性の病気」とは実は社会の方の適応障害。
感じすぎるわたしたちが壊れているんじゃなくて、
鈍感でいないと生きづらい世界が壊れてる。
追記メタディスクリプション
感受性が強い人は、他人の痛みを感じ取る高感度処理特性を持つ。
共感過多症、認知ラグ、感情飽和圏——それは病気ではなく、
世界を正確に感じている証拠。
#共感過多症 #現代の生きづらさ
感受性が高い人は服の質感や色のトーンにも反応する。
そんな人には着る環境を変えるのも一つの手。
このサブスク服サービスは感情の波をまとうみたいに日常を更新できる。


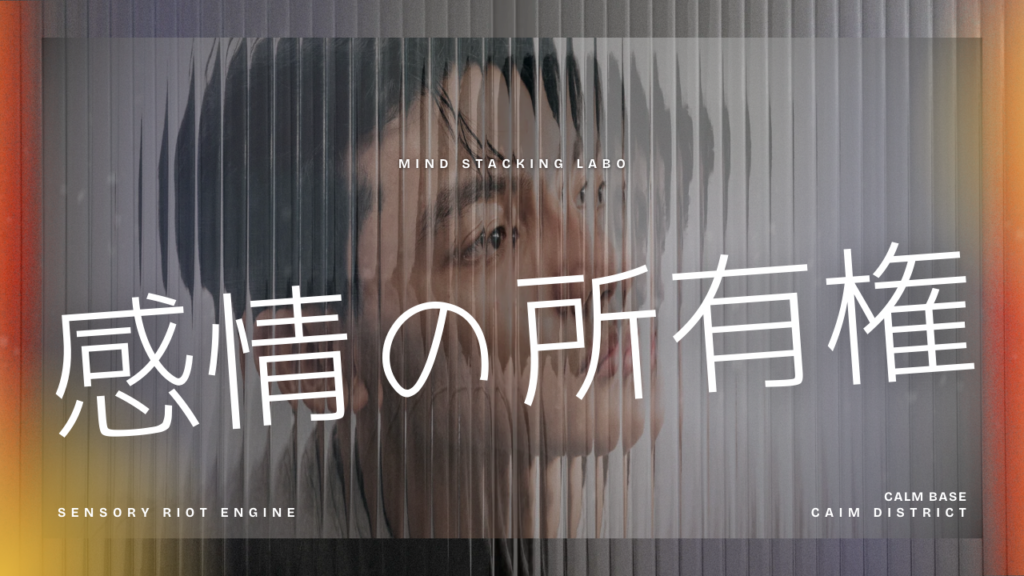









コメント